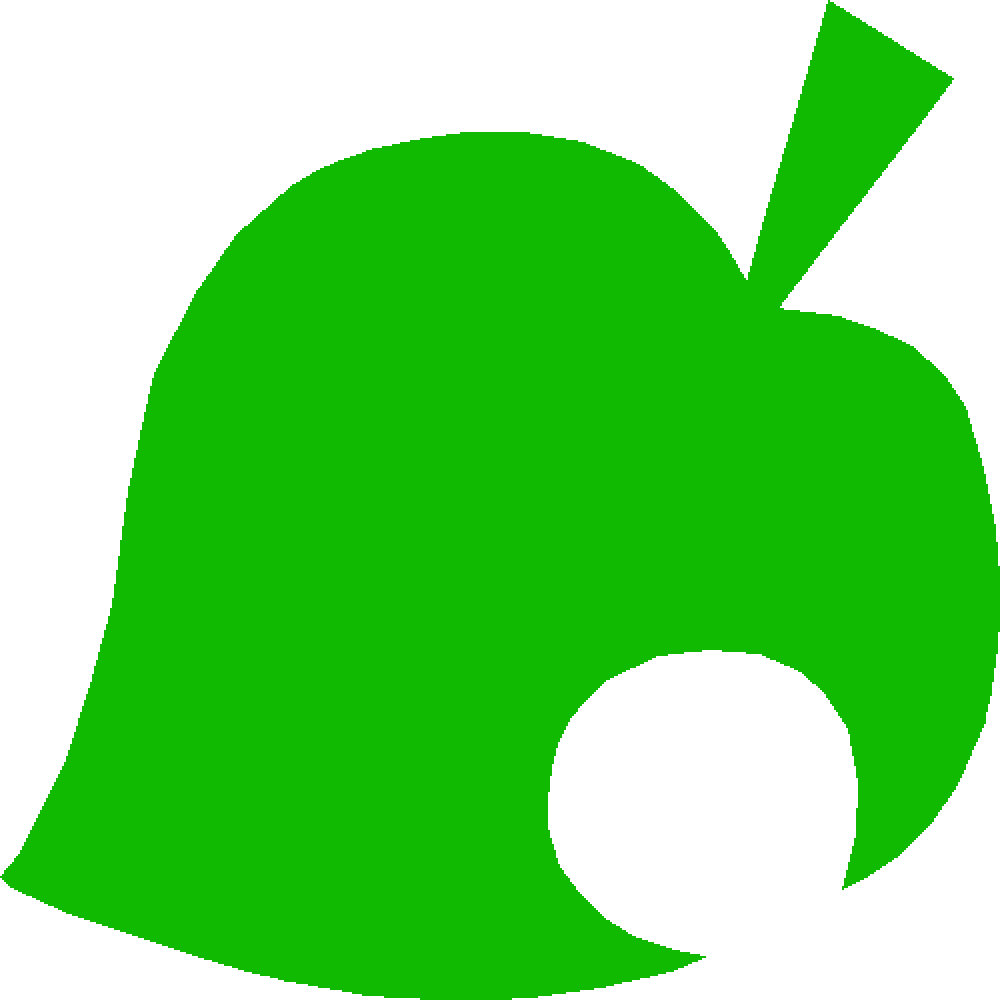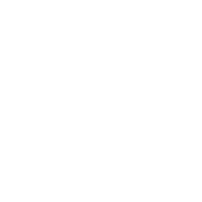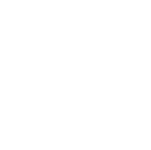| Num | 日本語 |
|---|
| アンモナイトの カラのruby直径は
ruby数センチ~ruby数十センチで
ruby海にruby棲んでいたとruby考えられる。
なかには ruby直径2メートルもの
ruby巨大なカラをruby持つものも いたらしい。 |
| コプロライトとも ruby呼ばれる
ウンコのruby化石は、ruby情報のruby宝庫である。
ruby運がruby良ければ、ruby中から ruby植物のruby種、ruby骨、
ウロコなどを ruby見つけることができ、
ruby何をruby食べていたかがわかる。
ウンコは ruby化石になりにくいので、
ruby希少価値のある ruby化石といえる。 |
| ruby恐竜のruby種類によって タマゴのruby大きさは
さまざまだが、ruby大きいものだと
30センチほどもある。
ふruby化するruby直前であれば ruby骨がruby見つかる
ruby可能性もあるが、ruby通常、どのruby恐竜の
タマゴかをruby見分けるのは とてもruby難しい。 |
| ruby元々、ruby植物はruby海のruby生きruby物だった。
シダは、ruby一番ruby最初のころに ruby海からruby陸に
あがったruby植物とされている。
ruby種ではなくruby胞子でruby増え、ruby形は
ruby今のシダとruby似ているが、ruby大きなものは
ruby高さが ruby数メートル あったらしい。
シダのruby森のruby化石は、
ruby現在 ruby石炭としてruby掘りruby出すことができる。 |
| ruby他のruby化石とruby違って、あしあとのruby化石は
ruby生きruby物が ruby生きていたruby時、
どのようにruby活動していたかのruby証拠となる。
ruby足型から どうやってruby体をruby支えて
どんなruby姿勢で ruby歩いていたかがわかったり、
どんなruby速度で ruby歩いていたかもわかる。 |
| ruby恐竜とruby鳥、ruby両方のruby特徴をruby持つので、
ruby鳥のruby祖先にruby近いruby存在といわれている。
ruby歯や ツメのあるruby三本のruby指をruby持つruby点が、
ruby現在のruby鳥との ruby明らかなruby違いである。
ruby体をruby軽くするために
ruby骨がruby空洞になっているので、
ruby化石としては ruby残りにくい。 |
| ruby約50ruby万年前にいた サルとヒトとの
ruby間にいるruby人種で、ruby石器をruby使って
ruby食料になるruby動物を しとめていたらしい。
ruby今のヒトの ruby直接のruby祖先ではないが、
もしかしたら ヒトのruby祖先と
ruby出会っているかも・・・。 |
| ステーキナイフのように
ギザギザになったふちが ruby特徴の、
ruby歯のruby化石。
サメは ruby恐竜たちよりも ずっとruby前から
いたが、ruby姿かたちは そのころから
ほとんどruby変わっていないと いわれている。 |
| ワラジムシにruby似た ruby形をしていて、
ruby海にruby棲んでいた ruby節足動物のruby仲間。
ruby体長は、4ミリ~70センチくらいだった。
ruby生物のruby中でも いちruby早くruby目をruby持ち、
ruby敵を ruby察知することができた。 |
| ティラノサウルスのruby名前でも おなじみの、
ruby恐竜時代を ruby最後までruby生きた
ruby最強最大のruby肉食竜である。
そのruby大きなruby体は 10メートルをruby超えるが、
たくみにバランスをとって ruby二足ruby歩行し、
ruby時速30キロくらいで ruby走ることができた。
ruby後ろruby足のruby鋭いツメで ruby獲物をおそい、
アゴのruby上下に ずらりとruby並ぶruby鋭いruby歯で
ruby肉をruby食いちぎり、ruby丸ruby飲みにしていた。 |
| ruby恐竜時代を ruby最後までruby生きた、
ruby三本のruby角と ruby大きなエリをruby持つ
ruby最大級の ruby草食竜。
エリは アゴのruby筋肉がruby発達したもので
ruby肉食竜よりも かむruby力が あったらしい。
ruby角は ruby身をruby守るためというよりも、
メスをめぐるruby争いや なわばりruby争いに
ruby使われていたようだ。 |
| ruby寒いruby気候にruby耐えるために
ruby長いruby毛におおわれ、ruby長大なキバをruby持つ
ゾウにruby似た ruby巨大なruby動物。
キバは ruby身をruby守るだけでなく
ruby雪かきをするにも、
ruby役立ったと ruby考えられる。
ruby数万年ruby前の ruby氷河時代のruby終わりに
ruby気候のruby変化によって ruby食料のruby草がなくなり、
ruby絶滅してしまったと いわれている。 |
| ruby顔からruby背中にかけて ruby鎧のようなruby装甲をruby持つ
ruby鎧竜のruby仲間にruby分類される。
ruby装甲は トゲや びょうのruby形をした
ruby骨でできており、なめしたruby皮のような
ヒフで おおわれていた。
しっぽのruby先には こんぼうのような
コブがついていて、ruby肉食竜におそわれたとき
ruby振りruby回して ruby身をruby守っていたらしい。 |
| ruby首としっぽが とてもruby長い
ruby巨大なruby草食竜で、あまりにruby体がruby重いので
ruby湖のruby中で ruby生活をしていたらしい。
ruby一般的にruby草食竜は ruby消化器官が
ruby肉食竜より ruby大きいので、
ずんぐりとした ruby体型のものがruby多かった。 |
| ruby恐竜時代のruby初期にruby生きたが、ruby歯のruby特徴から
ほにゅうruby類ruby型ハチュウruby類にruby分類され、
ruby恐竜ではない。
ruby肉をruby食いちぎる ナイフruby状のruby歯と
すりつぶすための ruby小さなruby歯をruby持つ。
ruby背中にあるruby大きなruby帆で ruby体温のruby調節をした。 |
| ruby発見されたruby時、ruby歯のruby形のせいで
ruby大きなイグアナだとruby思われたため、
このruby名前になったらしい。
ヤリのようなツメがruby特徴的な ruby草食竜で、
ruby走るときは ruby二足ruby歩行、ゆっくりruby歩くときは
ruby四足ruby歩行していたと ruby考えられている。 |
| ruby体はライオンくらいのruby大きさで
ruby上あごに ruby二本のruby長いruby犬歯をruby持った
ネコのruby仲間である。
マンモスなどがruby主食だったが、ruby気候のruby変化や
ヒトのruby乱獲によって それらがruby減少し、
ruby数万年前に ruby絶滅してしまった。 |
| ヘルメットのような
ruby丸いruby頭がruby特徴の ruby石頭恐竜。
ruby頭頂部のruby骨は ruby厚さ30センチもあった。
おruby互いに ruby頭をぶつけあって ruby群れのruby中での
ruby順位をruby決めたというruby説があったが
ruby今では あまりruby支持されていない。
ruby頭部のruby化石が ruby見つかることがruby多い
ruby恐竜である。 |
| カモノハシruby竜のruby仲間。ruby頭のトサカは
シュノーケルのようなruby形をしていて、
ruby鼻からruby頭のruby後ろのruby方へruby長くruby伸びており、
1メートルをruby超える ruby中空のruby骨で
できていて、ruby鼻からruby息をruby出すと
ruby低いruby音を ruby響かせることができたらしい。 |
| ジュラruby紀ruby後期の ruby体長30メートルをruby超える
ruby巨大なruby草食竜で、とてつもなくruby長い
ruby首とruby尾をruby持っていた。
ruby特にruby細長いruby尾は ムチのようにruby振って、
ruby敵からruby身をruby守るために
ruby使われていたと ruby考えられている。 |
| ruby日本近海にruby生息していた、
ruby首長竜という ハチュウruby類のruby仲間。
ruby全長は およそ7メートル。
ruby当時 ruby高校2ruby年生だった スズキさんが、
ruby発見したので このruby名前がついている。 |
| ステゴとは「ruby屋根におおわれた」という
ruby意味である。
ruby発見ruby当初、ruby背中のひしruby型のruby板で
ruby体がおおわれていたと ruby考えられたため
このruby名前がついた。
ruby板はruby骨でできていて、さらにruby厚いヒフで
おおわれていた。ruby体温をruby下げるruby役割が
あったとruby考えられている。 |
| ruby空をruby飛ぶruby翼竜のruby仲間で、ハチュウruby類である。
ruby翼をruby広げると ruby小型ruby飛行機なみのruby大きさで、
ruby体はruby軽く、20kgもなかったとされる。
ruby体のruby脇から ruby腕とruby脚にかけて
ヒフがはってruby翼になっており、ruby体のわりに
ruby軽かったので、ruby飛びやすかったようだ。 |
| ruby魚竜という ruby海にruby生息していた
ハチュウruby類のruby仲間で、
ruby見たruby目は イルカにruby似ていた。
おruby腹に ruby赤ちゃんのruby骨をruby持つruby化石が
ruby発見されており、ruby卵をふruby化させてから
ruby産みruby落としていたと ruby考えられている。 |
| ベロキラプトルともいわれる。
「ruby素早いruby略奪者」のruby意味である。
ruby体のわりに ruby頭がruby大きいので、
ruby高いruby知能を ruby持っていたのではないか
というruby説がある。
ruby体はほっそりしているが、ruby後ろruby足の
ruby大きなかぎヅメで ruby獲物の のどやruby首を
ruby突きruby刺し、しとめていたようだ。 |
| スティラコとは、「トゲのある」
というruby意味である。
ruby鼻のてっぺんのruby角のほかに、
フリルのような ruby派手なエリにも
ruby三対のruby角がruby生えていた。
ruby群れをなすように ruby化石がruby発見されたので
ruby集団でruby生活していた というruby説もある。 |
| ruby背中からruby長くruby伸びた トゲruby状のruby骨のruby上に、
ヒフがruby被さった ruby帆のようなruby突起がruby特徴。
ruby体温調節の ruby役割があったとruby思われる。
ruby主にruby肺魚とruby呼ばれる ruby泥にruby棲むサカナを
ruby食べていたと ruby考えられている。 |
| ruby鼻のruby上に ruby骨でできた Yのruby形のruby角をruby持つ、
サイのruby遠縁にあたる ホニュウruby類。
ruby水辺のruby柔らかいruby草を ruby食べていたが、
ruby気候がruby変わって ruby乾燥するにつれ
ruby草がなくなって ruby絶滅してしまった。 |
| 「ruby古代のカメ」というruby意味をruby持つ。
ruby全長4メートル、ruby体重は2トンという
ruby巨大なウミガメ。
クラゲやイカなどを ruby食べていたと
ruby考えられているが、アンモナイトも
ruby食べていたというruby説もある。
ruby今のカメとruby違い ruby柔らかいコウラだったので
ruby手足をruby引きruby込んで ruby体をruby守ることが
できなかったようだ。 |
| 「ruby古代のカメ」というruby意味をruby持つ。
ruby全長4メートル、ruby体重は2トンという
ruby巨大なウミガメ。
クラゲやイカなどを ruby食べていたと
ruby考えられているが、アンモナイトも
ruby食べていたというruby説もある。
ruby今のカメとruby違い ruby柔らかいコウラだったので
ruby手足をruby引きruby込んで ruby体をruby守ることが
できなかったようだ。 |